MGP NEWS 5月号


第30回!!クイズコーナー
4月クイズの答え
LDKと表記できる広さは何畳からでしょうか?
正解は、 2、「10畳から」 3、「8畳から」です。 今回は2つ正解とします。 居室が2部屋以上(2DK・2LDKなど)の場合は10畳以上をLDKと呼べますが、 居室が1部屋(1DK・1LDKなど)の場合は8畳以上でLDKと言えるそうです。
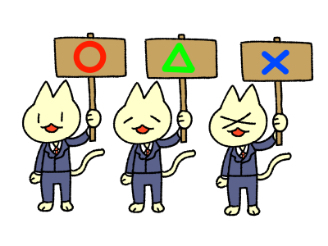
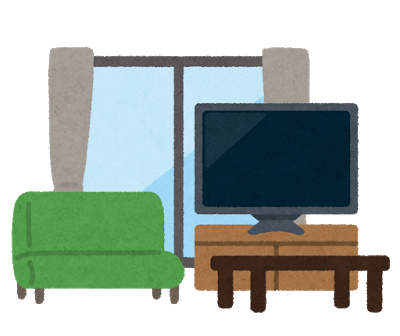
5月クイズコーナー
視覚障碍者の方も読書を楽しまれます。 ただ、方法が我々とはとは違います。 朗読のボランティアさんが、CDに朗読をした音声を録音してくださり、それを公立の図書館等で借りて専用の機械を使い音声で読書をされています。 さて、この音声での読書のことを何というでしょうか? 1、 副音図書 2、 デイジー図書 3、 ハイブリッド図書

森のくまさん


新年度が始まりました♪今年度もコロナ禍で新しい生活様式の中での保育となります。感染症対策を厳重に行いながら、森くまキッズにどんな楽しい保育を提供できるのかが大きな課題ですが、子ども達の成長に欠かせない経験はたくさんさせてあげたいものです。今年度も職員の体制を整え、一丸となり子ども達の為に頑張りたいと思います。パートの先生が多いので中にはご家庭の都合で残念ながら退職となる先生も多くいらっしゃいますが、その分また新しい先生達との出会いもあり、長く働いてくれている先生達も仕事を教える事でどんどんステップアップしてくれています。保育現場は子どもも大人も学び合い成長し続ける場所です。せっかく同じ時を共有しているのですから、集まった御縁を大切に、毎日にワクワクドキドキしながら楽しい時間を共有していきたいものです。
4月より仲間入りしました保育士の先生を紹介致します。
『初めまして、保科清美(ほしなきよみ)と申します。今回4月から森くまで働かせて頂く事になりました。宜しくお願い致します。一年間のブランクがあるので少し心配、そして不安もありますが頑張りたいと思います。今まで様々なアルバイトは経験してきましたが、仕事としては三十七年間保育士として働いてきました。この間には三人の子どもを育て、現在三十五歳を始め、三十一歳、二十八歳、そして孫4人に囲まれ賑やかに過ごしています。子ども達の小さな頃はキャンピングカーで夏休みを利用して北海道一周や四国一周、祭りめぐりと様々な所へ行き家族で楽しい思い出をたくさん作って来ました。現在は主人と二人の生活で、月一回の旅行、そして飛行機の旅行、畑で作物を種から育てわが子の様に育て収穫の楽しみにひたっております。お休みの日はじっと家にはいられず、どこまでも自転車で走り回って自然と触れ合っています。これからは森くまでの先生達、子ども達との出会いを大切に、「今日保育園に来て楽しかった。」と思える日が過ごせるように笑顔を絶やさずしていきたいと思っています。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。』
エチゴヤおすすめの商品紹介!

千葉の大仏巡り (乾坤山日本寺大仏)

鋸山にある日本寺は聖武天皇の勅詔と光明皇后のお言葉を受けた行基菩薩によって725(神亀2)年に開山。日本一の大仏(※)として知られる「薬師瑠璃光如来」は総高31・05m、御丈21・3mというスケールです。ちなみに鎌倉の大仏は総高13・35m、御丈11・312m、奈良の大仏でも総高18・18m、御丈14・85mなので日本寺の大仏の大きさがはるかにでかいということが把握できると思います。ただし現存する日本寺の大仏は昭和44年(1969)に復元されたものです。天明3年(1783)に初めて造られた当時のものはさらに大きく3年にかけて岩山を彫刻し御丈24・24m台座との合計が24・88mにもあったという。昭和の復元の際は、4年の月日をかけた大工事で世界平和と万世大平の象徴として建立されたものです。「近くで見ると大きさがわかって圧倒されます。でも千葉に日本一の大仏があるとは思いませんでした。なぜって鎌倉の大仏があまりにも有名だからです。でも千葉県民としては誇らしいです」日本寺の境内には千五百羅漢や百天観音、地獄のぞきといった見どころも多数あります。百天観音は世界戦死病没殉難者供養と交通犠牲者供養のために発願され6年の歳月をかけて1966年にかつての石切場跡に完成されました。以来航海、航空、陸上交通の安全を守る本尊として崇められています。コロナが終息したら千葉の旅をもう一度見直してみたいものです。
(※)磨崖仏(まがいぶつ)として日本一
今月も一句
風強し 遠くに見ゆる 五月富士 矢野
営業報告
営業担当(仮)の竹内です。早いもので現場を離れてもう1年が経ちました。まだまだコロナ禍で営業も厳しい中、日々努力はしていますが・・・
正直なところ、材木等の不足、高騰の影響で6月以降の着工状況がかなり厳しいとみています。そんな中、既存工務店や過去の工務店に声をかけたり、新規獲得に向けて頑張りますが、新規の獲得は簡単なわけではありません。なので既存、新規問わず職方の皆さんの施工精度、現場対応等でクレームなどがないようにして、また指名してもらえるような仕事を常に心がけてください。暇なときに文句を言われるのは営業として仕方ないと覚悟していますが、忙しい時や現場が遠いなどと文句を言うような人は、自分で営業してください。私は現場に復帰したいので、いつでも代わってあげますよ?(笑)
三咲事務所の菜園
今年も三咲事務所に様々な種類の野菜苗が植えられました!毎年、森社長が気合を入れて植えていらっしゃいます。今年の野菜はきゅうり、ししとう、ミニトマトなどです。夏になるとたくさん実を付けてくれることでしょう♪
皆さん三咲事務所に寄った際はぜひ野菜の成長をご覧になってみてください!



編集後記
去年の今頃、「来年の今頃には終息に向かっているといいな」と思っていたコロナウィルスですが、なかなか道は険しいですね。我慢の連続で皆さんつらい思いをしているかと思います。今夏開催予定のオリンピックも、果たして本当に開催できるのか、気になるところです。1年後はこの編集後記で明るい話題が出せる世の中になっていることを、
切に願っています。